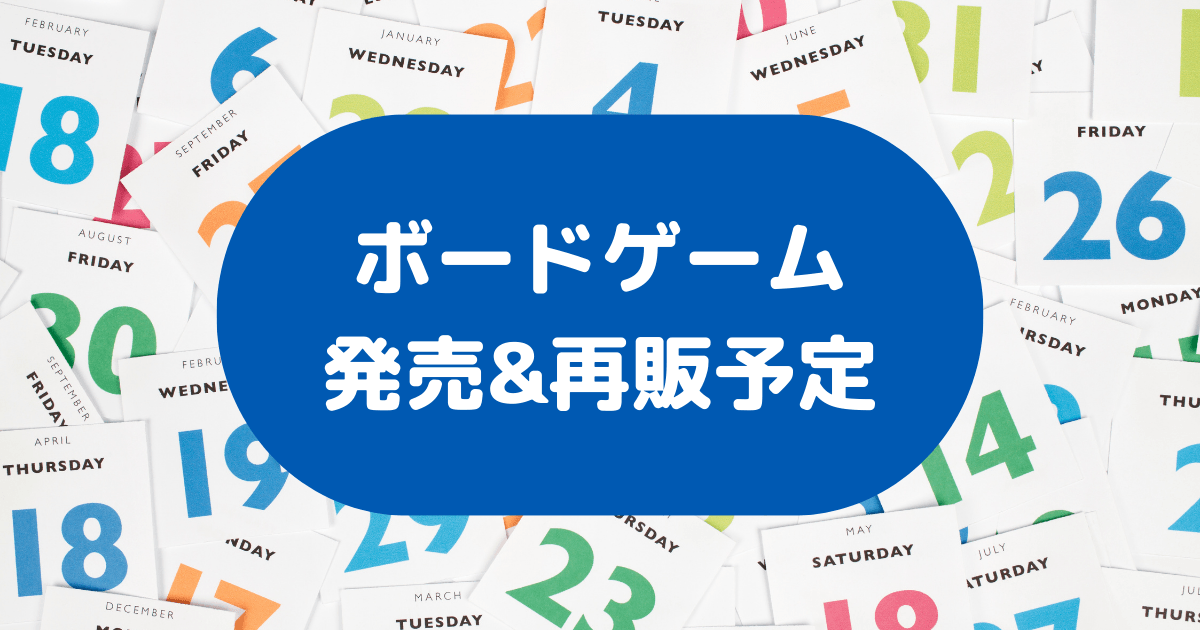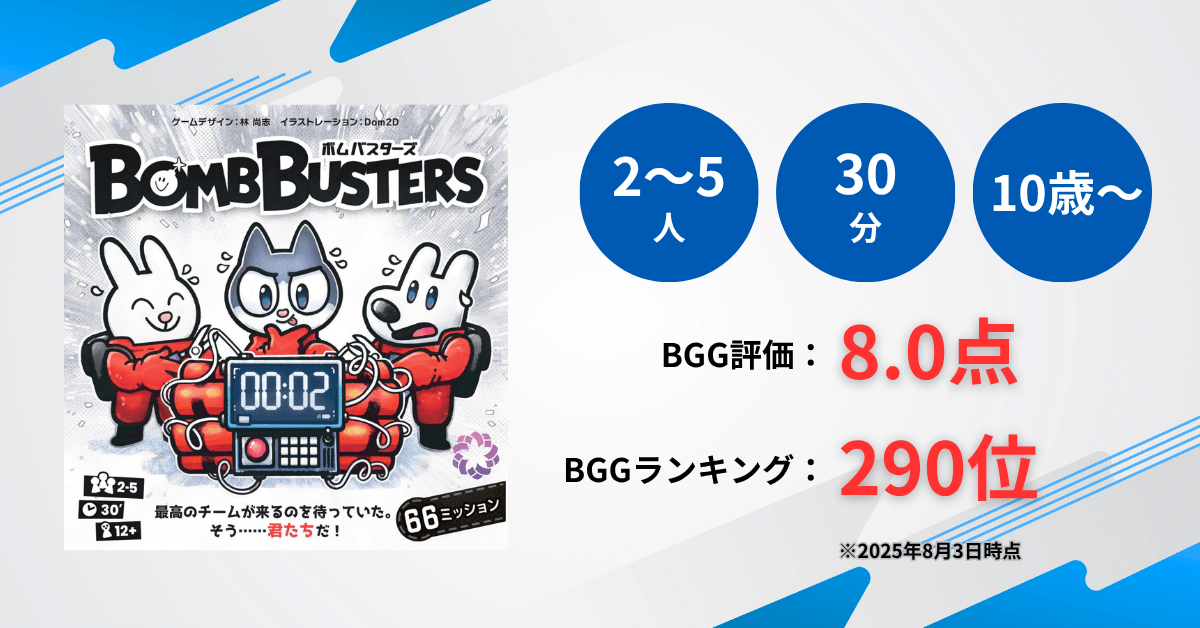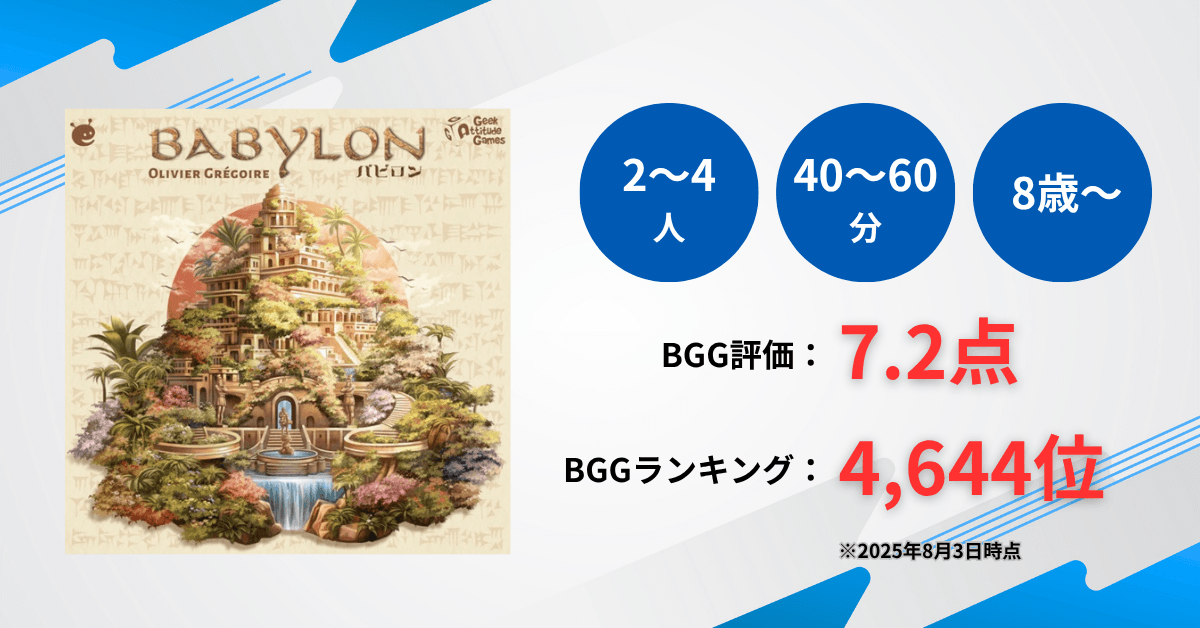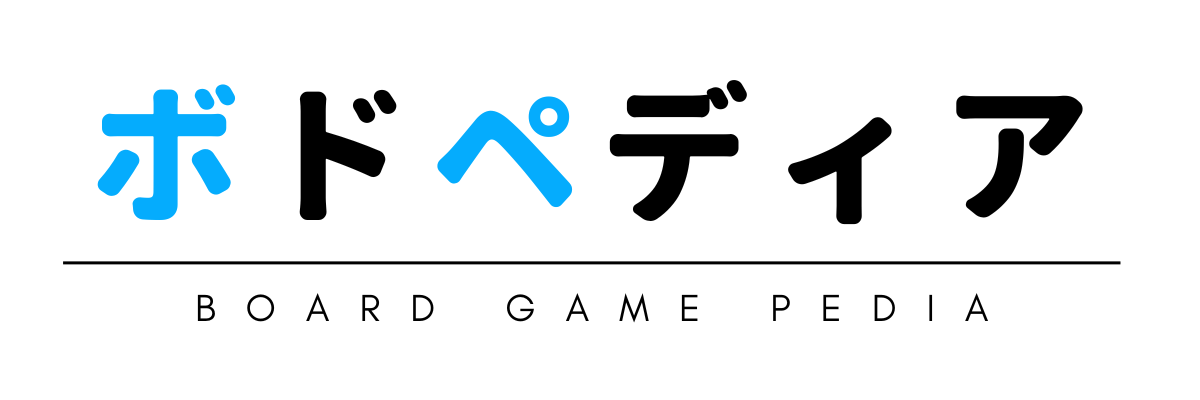ボードゲームに因んだ小説を書いてみました!
今回テーマは『ラー』
並んだタイルを得るために、いくら払うのか。塩梅が絶妙で面白い作品。
でも、もし調子に乗りすぎてしまうと……?
タイトル:全ては、神のみぞ知る

――全ては、太陽神のままに。
ここは、太陽神の御業によって国の繁栄が決まる、不思議な世界。
太陽神が現れたら国の繁栄を賭けた恵みを得るためのオークションが始まる。
その参加者は各国の主たちだ。
このために自国からかき集めた資産を供物とし、遺跡や遺産、オアシスや金貨といった恵みを得る。
恵みはランダムにオークション商品として陳列されていくため、時には干ばつや災害など、望んでいないものが並ぶときもある。
しかし、神の気まぐれとして時には受け入れなければならない。
神は、気まぐれだ。気まぐれで、慈悲深い。
オークション商品として神の降臨を引き当てれば、神が舞い降り、オークションが始まる。
そうして、各国は恵みを競り合う。
一方で、望めば神はやってくるときがある。
ただし、神を呼ぶのは傲慢な行いだ、人はその責任を取らなければならない。
必ずどこかの国が、オークションで恵みを落札し、用意した供物を捧げないといけない。
そんなゲームのような世界で、国々の王は神と共存している。
「王様!また太陽神様をお呼びになったのですか!?」
「ああ、呼んだ。」
「全く……今回も隣国が名乗りを上げてオークションを終えてくれたから良いものを……誰も名乗りを上げなかったら王様が供物を捧げないといけないんですよ!?」
「なに、心配ない。」
ラーを呼び出す権利を持つのは、この世界の王たちだ。
周辺国がオークションを辞退すれば、ラーを呼び出した本人が供物を捧げるというのが、この世界のルールだ。
それゆえに、ラーを呼び出すのはリスクだ。
大人しく降臨を待っていた方が安全であると、滅多に呼ばれることのないラーを、かの王は頻繁に呼び出していた。
そんな不思議な世界で、ある国を統べる王。
安定した統治で内外共に『賢帝』と呼ばれていた。
「余の予想通りであっただろう?」
外交に長けている賢帝は自信に満ち足りた様子で足を組む。
「干ばつが並んでいたが、あの遺物は隣国が喉から手が出るほどに欲していたものだ。隣国が捧げざるを得ないと読めていた。」
周辺国の供物事情、内情、欲している恵みについて、かの王は全て把握していた。
「だからって、なぜそんなにも太陽神様を頻繁にお呼びになるのですか?」
「恵みの羅列を独占するためだ。」

各国が供物を捧げ、恵みを得られる回数は取り決められている。
一国が一方的に供物を捧げ続け、他国が恵みを受け取れずに破滅するのを避けるためだ。
全ての国が恵みを受け取るまで、太陽神ラーはこの世界に現れ続ける。
ラーが現れ続ける限り、恵みの陳列は続く。
限度回数を超えた国は、その国を受け取る権利を失う。
この王は、己が最後に恵みを受け取る権利を得るため、世界を回すようにラーを呼び出した。
周辺の国々は供物を捧げる機会をどんどんと失くしていった。
「恵みを受ける権利を持つのが我が国だけになれば、恵みを受け取り放題だ。我が国は世界一豊かな国になる。」
「さ、さすが我が王……!!」
賢帝の理想通りに進んでいき、やがて周辺国の資産は底をつき、恵みを受ける限度回数を迎えた。
残っていたのは賢帝が統べるかの国のみ。
「余の理想通りだ!!!!」
恵みが羅列されていくのを眺めながら、賢帝は両手を広げて高らかに笑った。
遺産や遺物の中に干ばつと災害も入ってしまったが、豊潤な恵みだ。
これを自国の言い値の資産を供物として受け取ることができるとは。
賢帝は漏れ出る笑いを止められない。
『我を呼んだのは、汝か。』
ある恵みが出現した時、ラーが姿を現す。
神が人々の目の前に現れるのも、また恵みの一つだ。
いつ何時、神が出現する恵みが並べられるかは、まさしく神のみぞ知る。
「はっ、ラー様。この度はありがとうございます。こちらが供物になります。」
賢帝はラーに恭しく頭を垂れる。
『うむ、確かに。では汝にこの恵みを授けよう。』
光り輝く恵みが散っていき、ラーは姿を消した。
「こんなにも恵みが!やはり余は正しかったのだ!!」
賢帝は歓喜の雄叫びを上げる。
なぜなら、この国の供物を捧げる回数はあと一回、残っている。
「さぁ、神よ!我が国に恵みをお与えください!!」
恵みが再び陳列されていく。
求めてやまない遺産や壁画が並んでいった。
「これで、残りの供物を捧げれば恵みが、」
『我を呼んだのは汝か?』
「めぐみが……は???」

今後の自国の繁栄を確信した賢帝の王の前に再び神が現れる。
恵みの中にあるラー降臨が発動した。
この世界では、恵みの陳列でラー降臨が現れる回数が規定されている。
陳列棚の背後には石板があり、光で規定回数を教えてくれる仕組みになっている。
王は気づいていないようだが、この規定回数に達してしまっていたようだ。
その場合、恵みを捧げる機会は強制的に失われる。
これ即ち、賢帝に供物を捧げることができなくなってしまうということだ
呆然としていた賢帝はハッと我を取り戻し、ラーに縋る。
「かっ……神よ!供物ならここに!!なので恵みを」
『恵みが欲しいのならば、汝が自ら呼べばよかったものを。』
そう、各国の王たちは自らラーを呼べる権利を持つからこそ、最後にラー降臨の恵みが出現してしまえば、神からの授与は終わるのだ。
「そ、その通りでございますが、この度ラー様をお呼びするのを失念してしまい……」
『我の記憶では、自ら我を呼んでいたのはほとんど汝であろう!供物を捧げる権利は十分にあったはずだ。』
賢帝は言葉に詰まる。
『恵みの陳列で我が降りてくる可能性があることなど、聡明な汝なら容易に予想できたことだろう』
「そ、そんな……!あの恵みがないと我が国は滅んでしまいます!!!」
『くどい!!!最も余を呼び出していた汝が供物を差し出さなかったのだから、余の恵みは不要ということだろう。何度も言わせるな。その口を閉じないようなら』
目には見えない神の圧力が王に直撃し、彼はよろめいた。
『国ごと、滅ぼしてやろうか。』
王はようやく何をしても無駄だということを理解し、へなへなと地面にへたり込む。
『では次回の恵みの時まで、我は眠るとしよう。これからも励むがいい、人間よ。』
そうして、太陽神ラーは並べられた恵みと共に、姿を消した。
王と彼が率いる国に残ったのは、捧げることのできなかった供物と、少しの恵みだけだった。
それからというもの、『賢帝』と呼ばれていたかの王は『愚帝』と呼ばれるようになり、国は恵みの時まで貧困を強いられた。
この愚帝の過ちを二度と犯すまいと、彼の所業は各国の王たちに語り継がれることとなる。
かの王は、望み通り、名前を残すことができた。
神の怒りを買いかねない愚かな行為を行った史上最悪の愚王として、この世界の歴史に名を残したのだ。